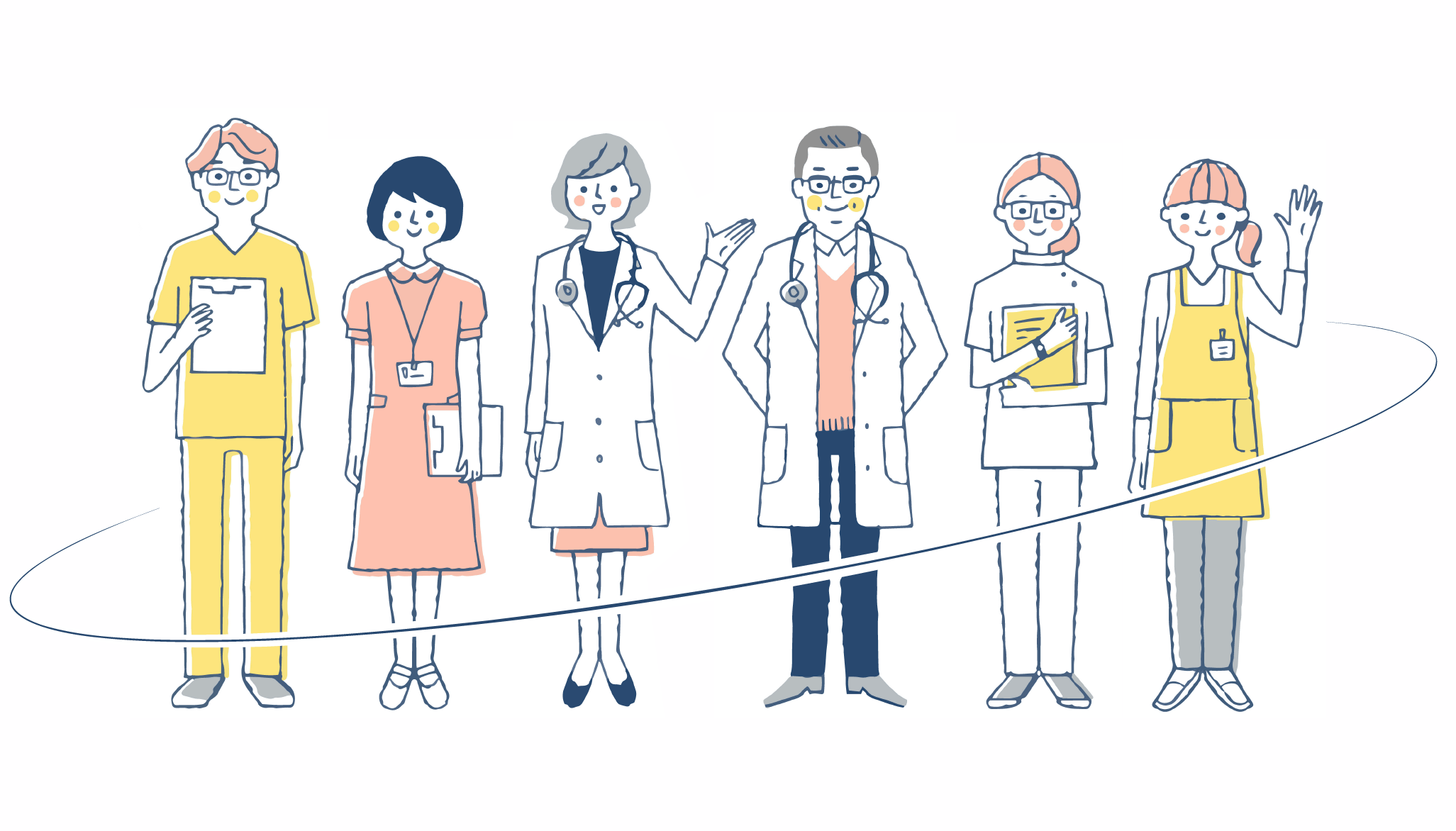
はじめに
Drug allergyを日本語に訳すと、薬物アレルギーあるいは薬剤アレルギーといいます。言葉の意味は似ていますが、薬物アレルギーの方が範囲が広いと見なされています。薬剤は通常、患者に投与される薬を指します(市販薬も含みます)。これに対し薬物は、投与薬に加えて、医療機関でたまたま接する物質(例として、処置で使われる手袋の成分や、物品の消毒に用いられた物質に触れる、など)や、医療機関の外で触れる物質(例として染毛剤の成分など)も含んでいます。ここでは、薬物アレルギーの話をします。

診療における課題と展望
昔は、薬物アレルギーを理由に受診する患者さんはほとんど見かけませんでした。実際には患者さんはいろいろな要望を持ち、そして一部の方は誤解を抱えたまま(表1)、誰に相談すれば良いかわからず過ごしているようです。最近少しずつ受診が増えてきていますが、どの医師にかかれば良いかわからないという声をよく耳にします。皮膚科の医師は、薬剤で誘発された蕁麻疹など様々な皮疹を見慣れているので、皮膚の症状に関しては皮膚科に受診するのが良いでしょう。全身症状が生じるアナフィラキシーや、内臓の症状に関しては、医師の側も、薬物アレルギーを診療する機会や、トレーニングの場面がほとんどなかったというのが実情です。アレルギー専門医の間でも経験度にはかなり差があります。このような状況を変えていくために、アレルギー学会では専門医の知識・経験を補強するよう活動を強化しています。以前から学術集会で薬物アレルギー、重症薬疹、アナフィラキシーは扱われていましたが、それに加えて、総合アレルギー講習会や相模原臨床アレルギーセミナーでは必ずそれらが取り上げられて多くの参加者が聴講しています。講習会で皮膚テストの実習は常に人気があります。薬物アレルギーは小児よりも成人に多いことがわかっていましたが、鑑別を要することの多い食物アレルギーが最近は成人でも増加傾向にあり専門医の間で注目されています。薬物アレルギーのガイドラインは今までありませんでしたが、アレルギー総合ガイドライン2022の第12章として初めて作成されました。このような情勢の中で内科など各科のアレルギー専門医がカバーする診療範囲が広くなれば、薬物アレルギーの診療体制も今後充実していくことが期待されます。

基礎知識
薬物が投与されて生じる、目的としていない人体への悪影響を有害薬物反応(adverse drug reaction, ADR)と言います。副作用とも呼びます。皮膚、神経、肝臓、血液、肺など様々な臓器に副作用は生じます。副作用は非免疫介在性反応と免疫介在性反応に分けられ、大部分(75〜80%)は予測可能な非免疫介在性反応です。抗菌薬を内服すると腸内の細菌が打撃を受けて下痢になりがちですが、これは予測可能な反応です。一方、20〜25%は、予測不可能な反応であり免疫系を介するものと介さないものがあります(図1)。「薬物アレルギー」は副作用のうち5〜10%を占めるとされ、特定の薬物に感作された患者において生じる、薬物に対する免疫介在性反応です。
以前に行われた東京都内の事業所職員の調査では、約15人に1人は薬剤による過敏反応の既往を持つと報告されています。
重篤な薬物アレルギーは生命の危険に繋がることがあります。特に有名なのは、重症薬疹とアナフィラキシーです。筆者は内科医なので、薬疹よりはアナフィラキシーに関する相談を受けることが多いです。薬物による致死的なアナフィラキシーは抗菌薬、造影剤、手術で用いられる筋弛緩薬などの注射薬が原因であることが多く、急速に全身に拡散してアレルギー反応が一気に進むことが理由です。

2018年に日本医療安全調査機構は、医療事故調査制度での報告事例を分析し、「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」と題して、医療者に向けて6つの提言を行いました(表2)。いずれも重要な教訓です。
薬物ごとに、アレルギーの起こり方、対策には特徴があります。抗菌薬アレルギーは臨床現場で比較的多く起こります。ペニシリンにより起こるアナフィラキシーは典型的なIgE介在性反応です。ペニシリンを含む大きな分類であるβ-ラクタム系抗菌薬でアレルギーが生じた患者に対して指導を行う際は、(1)βラクタム系抗菌薬を全て避ける、が無難です。しかし避けるだけでは治療が不十分となることも起こりえます。(2)βラクタム系抗菌薬のうちで系統が異なる抗菌薬を選択する(ペニシリン系抗菌薬でアレルギーが生じた場合はセフェム系あるいはカルバペネム系を選ぶ)という対応法も現実に行われますが、側鎖が同じ薬物はリスクが高いので避ける(図2)、皮膚テストを行なって陽性反応が起きないことを確認してから使用する場面もありうる、といった点を頭に置くことが望ましいでしょう。キノロン系抗菌薬ではIgE依存性反応を起こすことは少なく、マスト細胞表面の受容体MRGPRX2に結合し細胞を活性化させる機序が最近注目されています。
造影剤に対する過敏症の既往がある患者はもちろんですが、喘息患者でも造影剤の使用は避けるのが望ましいとされています。具体的な対応はガイドラインを参照ください。
局所麻酔薬は歯科治療の際によく問題となります。麻酔薬を注射されてドキドキする、息苦しい気がする、といった症状が生じても、アレルギーではないことがほとんどです。局所麻酔薬はエステル型、アミド型があり、安全な薬を急いで一つ選ぶという場面では、以前に体調不良を生じた薬とは別の型を選ぶのが無難でしょう。
新型コロナウイルスワクチンの接種後にアナフィラキシーが起きることがあり、注目を集めました。殆どが女性で、PEGやポリソルベートが原因物質であろうと考えられています。他のワクチンでも(あるいは他のほぼ全ての薬剤でも)同様ですが、使う直前にアレルギーを生じる・生じないを正確に予知するのは不可能です。


診療の流れ
患者さんが過去の薬物アレルギーについて相談のため受診したと仮定しましょう。最も重要なのは、正確な記録です。薬を何時何分に内服し、何分(あるいは何時間)後にどのような症状が生じたか、医療機関で受けた診断と治療と指導内容、できれば食事の詳細も記録しておくことが必須です。正確かつ詳細な経過記録があって、初めて原因薬を絞り込むことができます。医師は記録内容と過去の報告例を照合して、指導あるいは検査を立案します。もし空腹で1種類の薬を内服し、30分以内にアナフィラキシーが生じて病院に救急搬送されてアドレナリン筋注治療を受けて回復したのなら、検査をすることなく原因薬を特定できるでしょうが、実際はもっと複雑な経過をとることが多いです。

内服を継続している薬物が体調不良の原因と疑うなら、薬物を変更あるいは中止してみるのがお勧めです(予め主治医と相談する方が良い)。どうしても原因薬を突き止めたい場合に、負荷試験(チャレンジテスト)を行うことが稀にありますが、多くはありません。起きうるアレルギー症状に対して対応できることが条件となりますので、重症薬疹や重篤なアナフィラキシーショックに関して負荷試験は行わないのが原則です。
アレルギーを起こしうる薬物をどうしてもまた使わざるを得ない場面があり得ます。ごく少量から開始して徐々に増量していき体が受け入れるよう誘導する手法を脱感作と言います。代替薬を使用すれば済む場面では、わざわざ脱感作を選ぶ必要はありません。
昔アレルギーを起こした薬物を一生避けるべきであるかは今も議論が続けられています。薬の品質向上のおかげで問題を起こしやすい不純物は昔よりも減少していますし、長年の回避でアレルギー体質が弱まる結果、今は当該薬を避ける必要がないということもあり得ます。欧米ではペニシリンアレルギーについて積極的に再検査してアレルギー体質が残っていないと分かれば使用可能と扱う流れが強まっています。アレルギー体質のレッテル(ラベル)を消すという意味で、delabelingと呼ばれます。
冒頭で表1に示したような患者さんの要望に関しては、実際に起きていたアレルギー反応の状況や、検査のリスクに対する患者さんの考え方、薬を使用する必要度や代替薬の有無により説明内容が変わってきます。全ての薬の安全性・危険性を調べてほしいという要望に関しては、検査がないという理由でお断りしています。私は「この薬はあなたにとって安全です」とは言う事はありません。「安全性が高い」「あなたにとってこの薬のリスクは、普通の健康な人が内服する場合と同じくらい低い」と説明しています。






